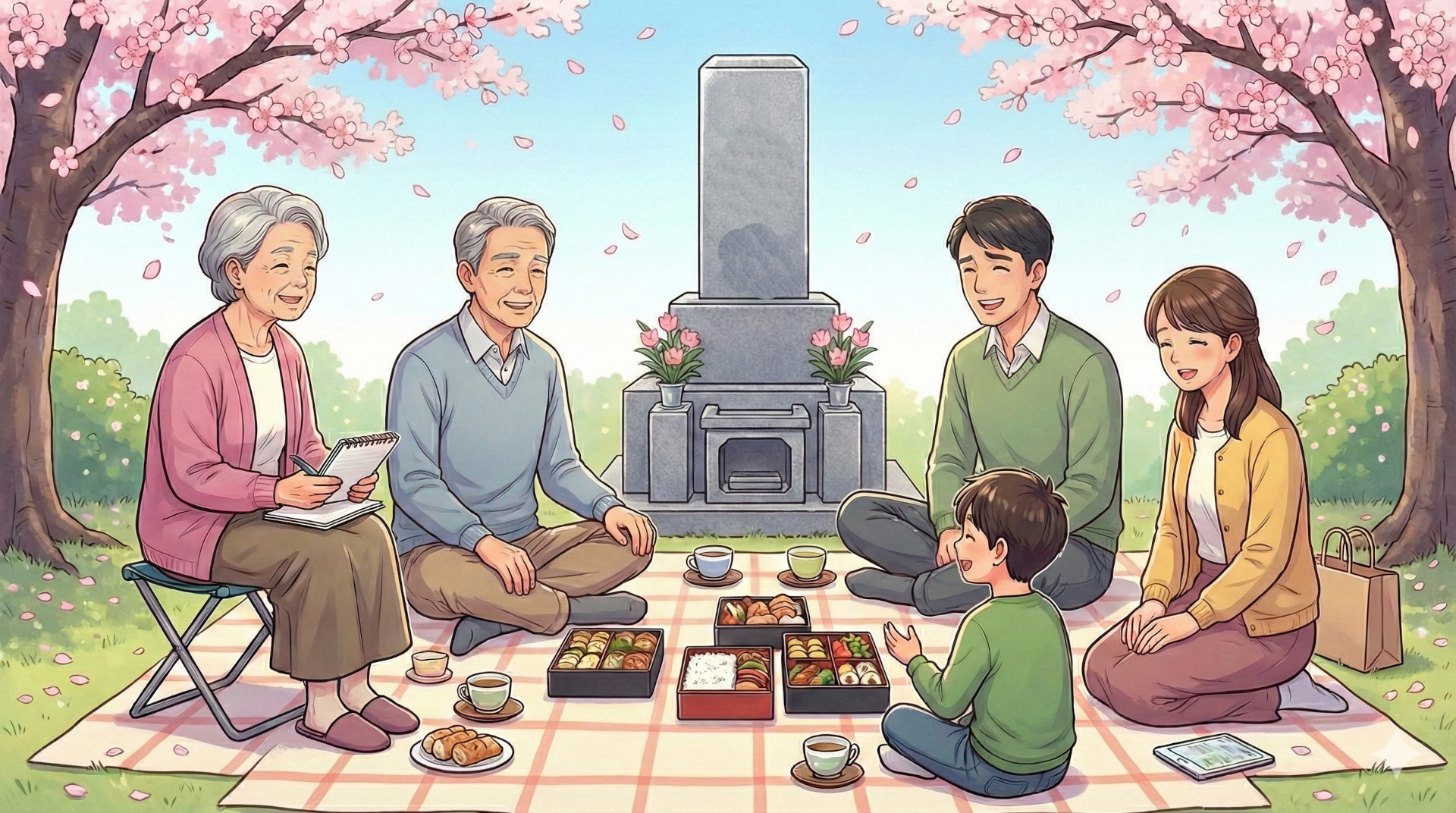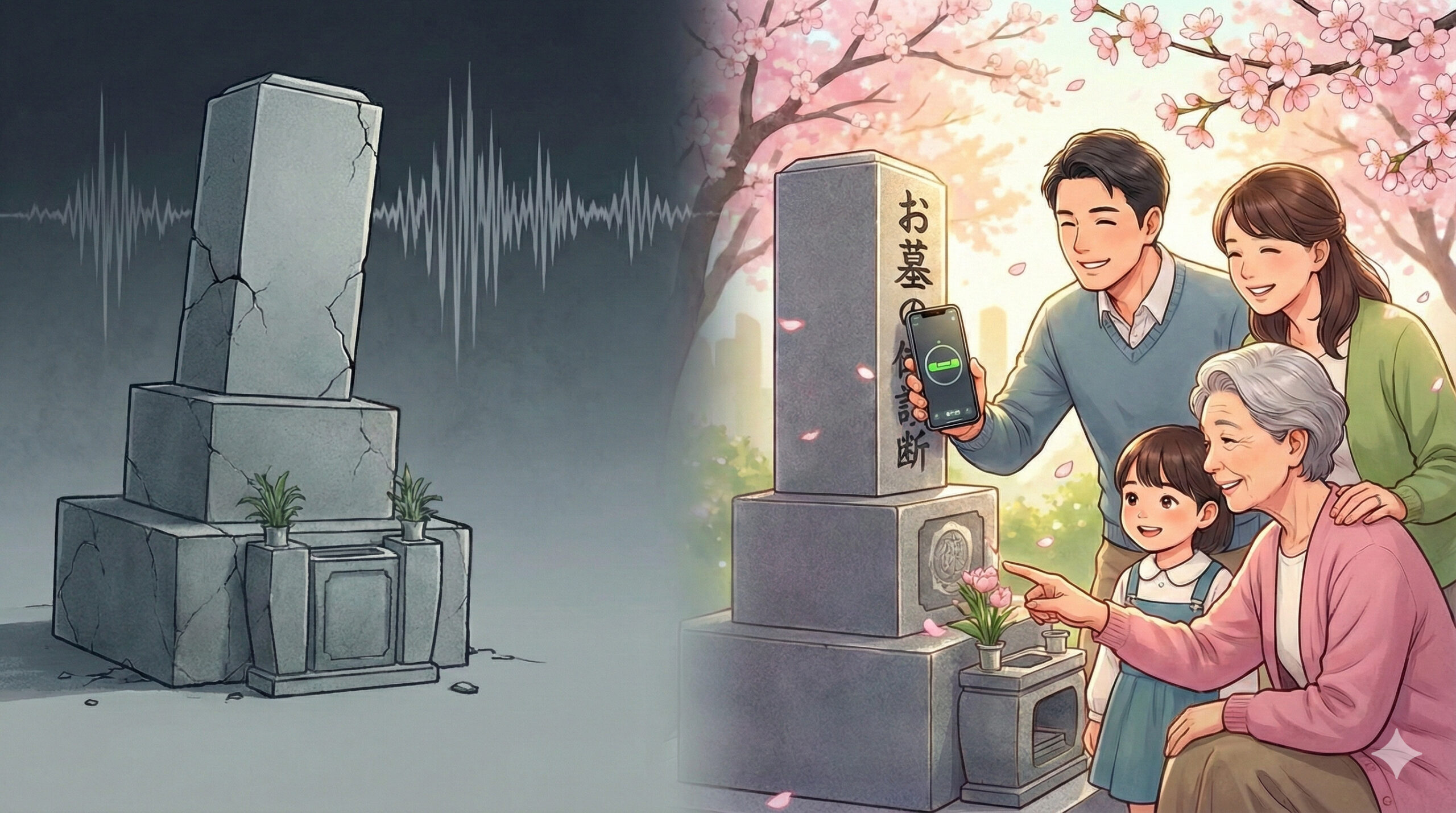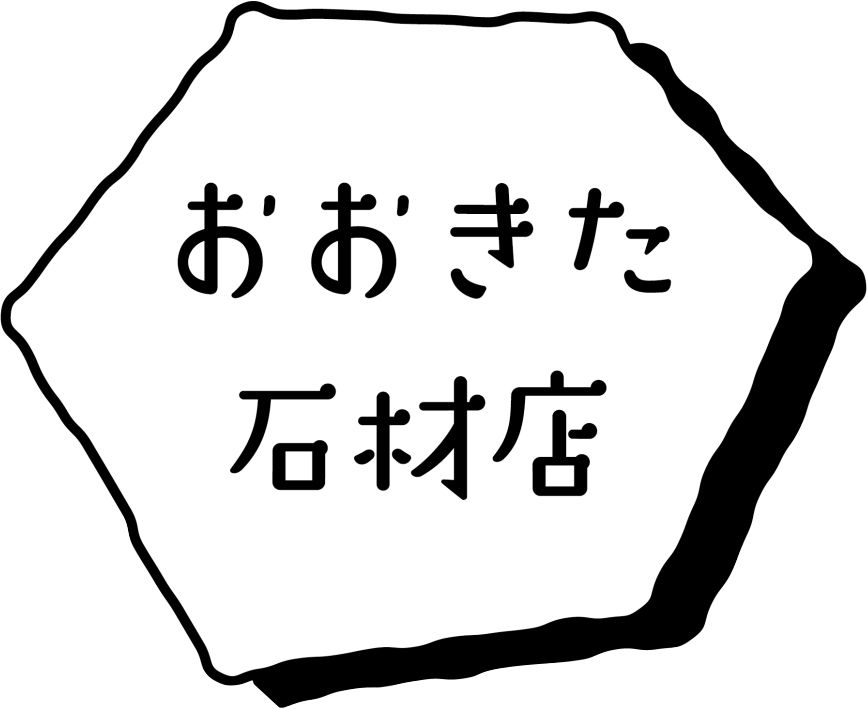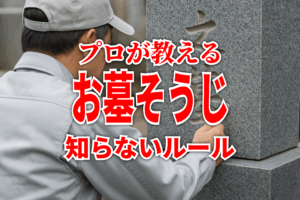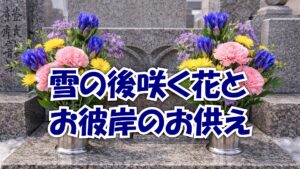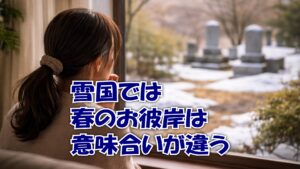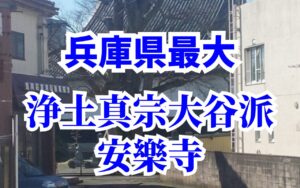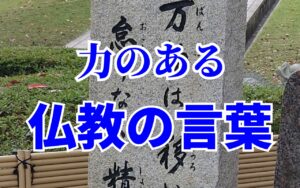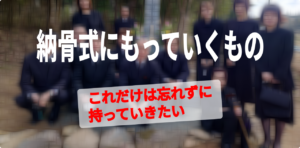今日はお盆なので、普段と違う、お盆ウイークの記事です。
友人の石材店店主であり、真宗大谷派教師でもある、㈲光德石材の山田昌史さんのブログを見ました。

山田さんからはいつもいろいろなことを学んでいて、特に真宗に関してはいろいろ教えていただいています。その山田さんがブログを投稿されていて、それを読ませていただきました。
お盆に鬼灯(ほおずき)をお供えする意味が書かれていました。
お盆と鬼灯
お恥ずかしながら、全く理由も考えず、そう言えば、いつも母が作ったお盆のお花には鬼灯が入っていたな、くらいしか思い出せなかったんです。鬼灯が入っていれば、目立つからいいのでは、くらいにしか認識していませんでした。

鬼灯にはとても大切な意味があったんですね。
亡くなった方の道案内。そして、目印。魂を導くもの、だから「鬼灯」という言葉の当て字にも意味があったんですね。どうしてこういう字で「ほおずき」と読むのか、全く知らなかったんですが、そこにも長い間、日本人が大切に守ってきた願いが込められている、ということですね。
「鬼(おに)」という字にも「魂(たましい)」という肉体と別れた人という意識に近い文字だったんですね。現代人の考える鬼とは、少し違う、もっと近しい、そして懐かしい存在だったのかもしれません。

大北家のお墓参りも私の母と娘の3人でお墓参りしてきました。
鬼灯がたくさん並んだ、分かりやすい、目立つお墓になったと思います。
鬼灯のこともそうですが、古くから日本人はとても深く意味とか意義とかを考えていろいろなことを慎重に今風に言うならば、「伏線を貼りながら」。
伏線を貼っていた日本人
それを伏線ではなく当たり前のこととして、生活していたんだな、と感じました。
現代の日本人はそれを知らなくて、時々そういう理由がわかると、「伏線」として感じてしまう。
でも私はそれでいいと思います。それが当たり前であれ、伏線であれ、見出して、取り入れるのが日本人らしい部分。まだまだたくさんの伏線が隠れていそうです。
隠れている、たくさんの伏線を探してみましょう。