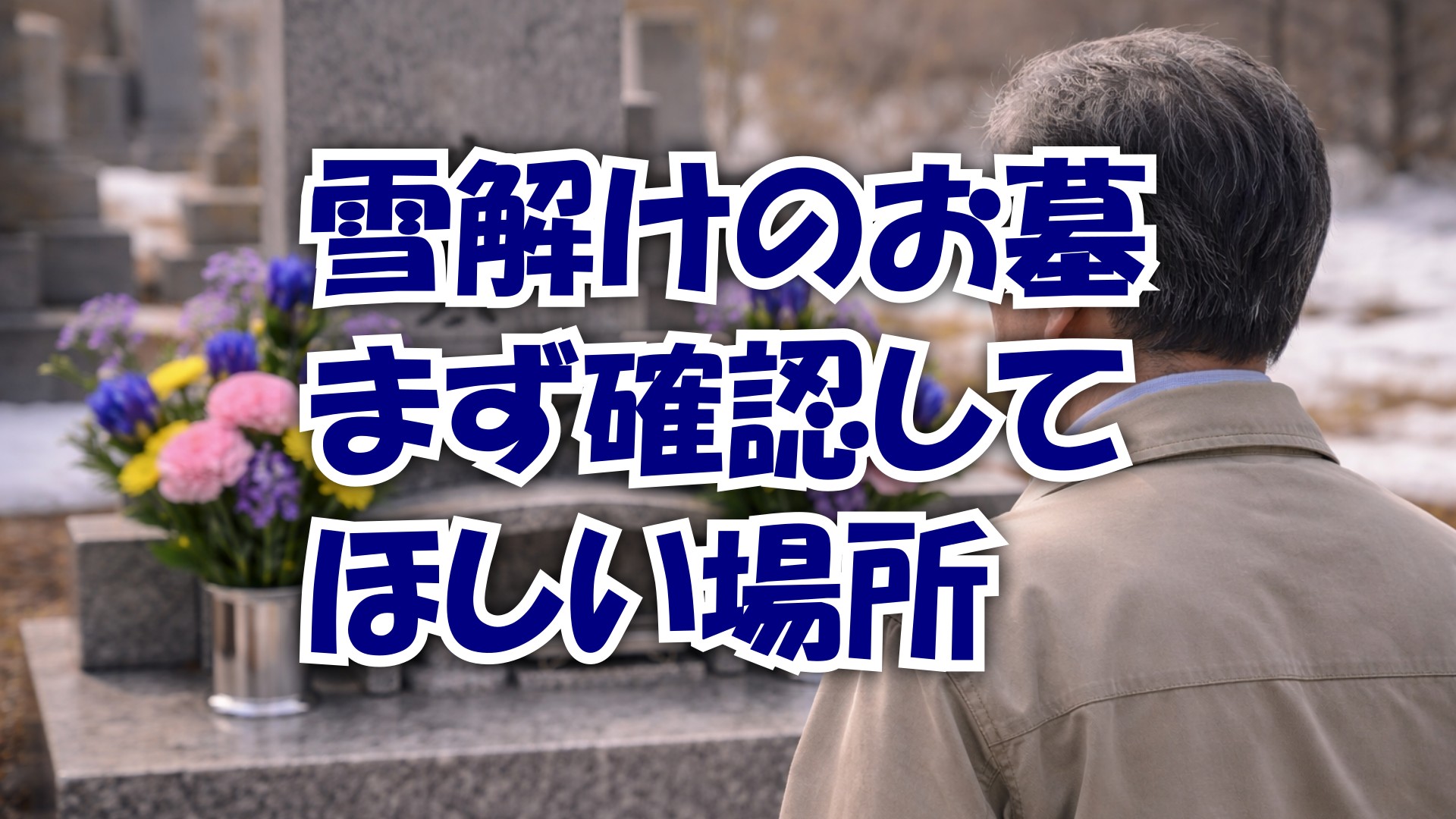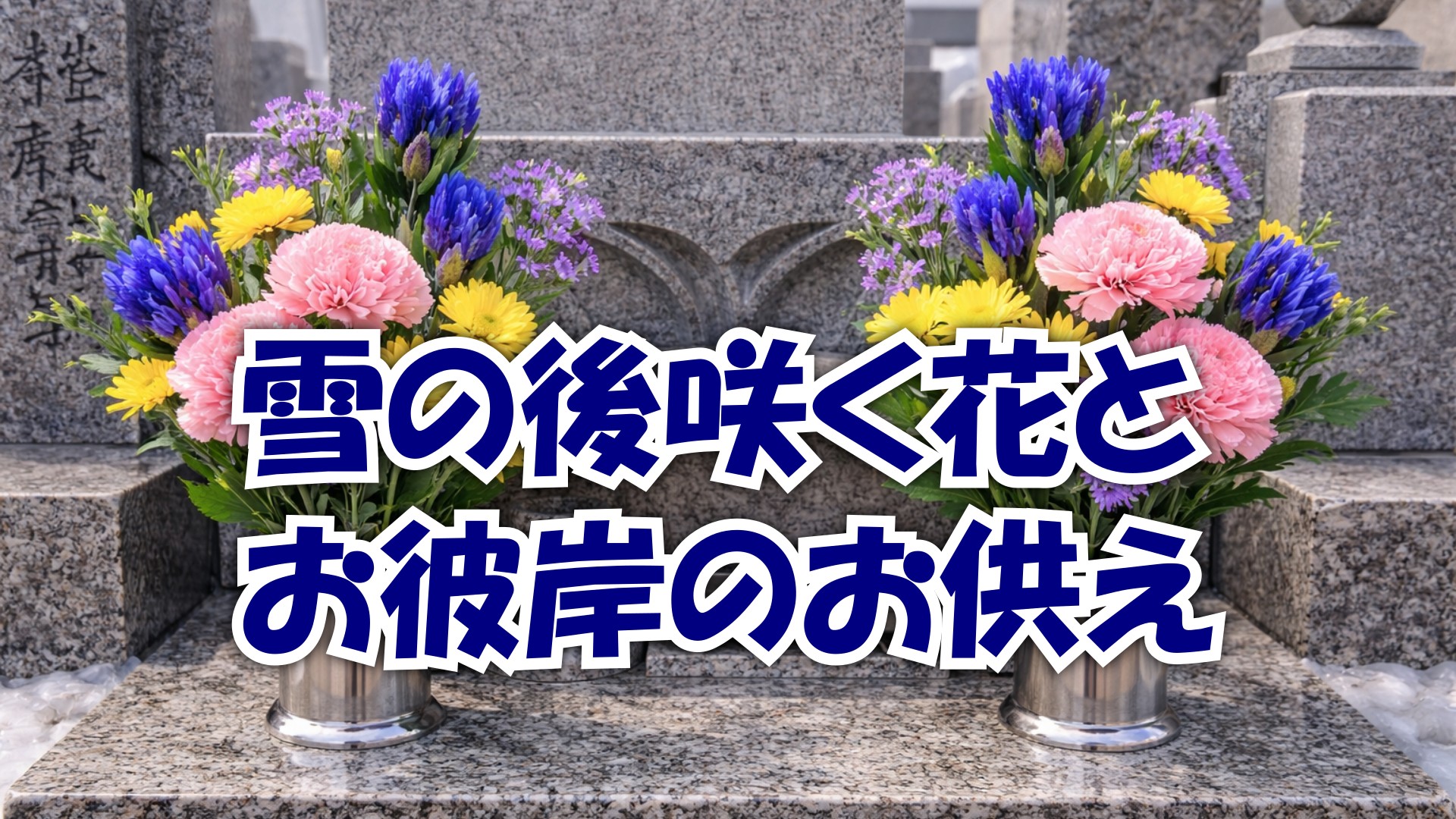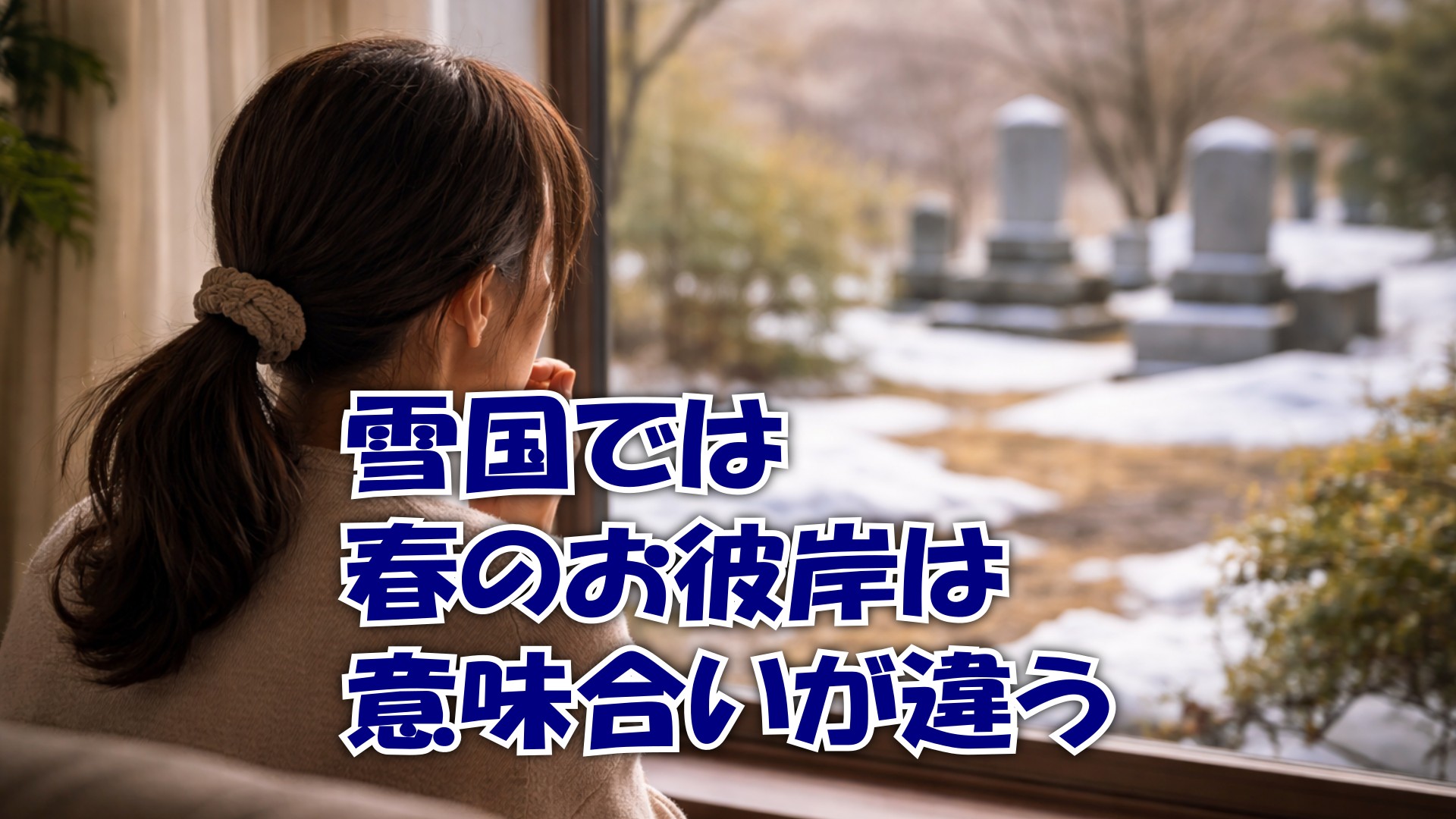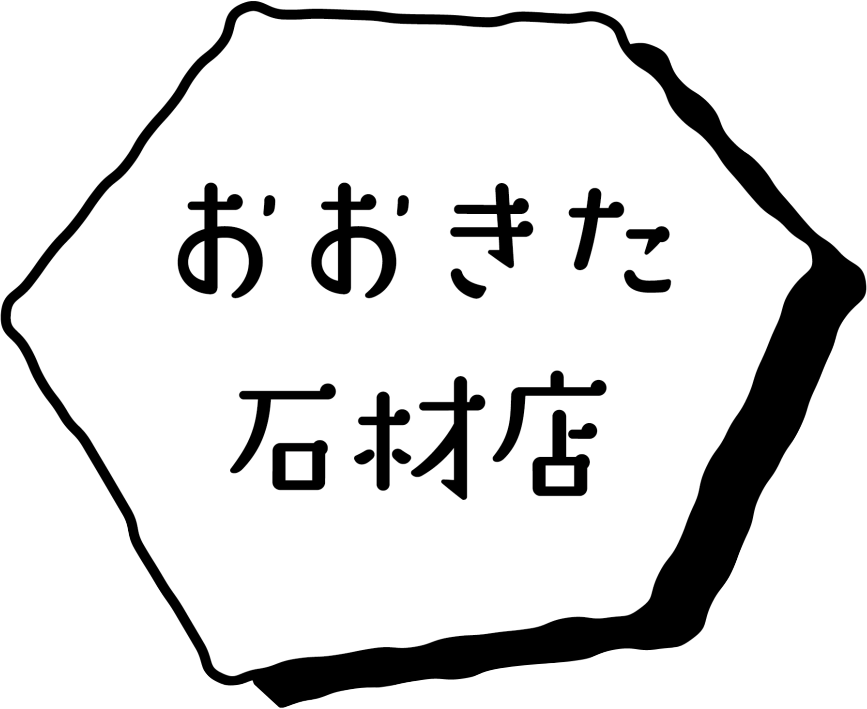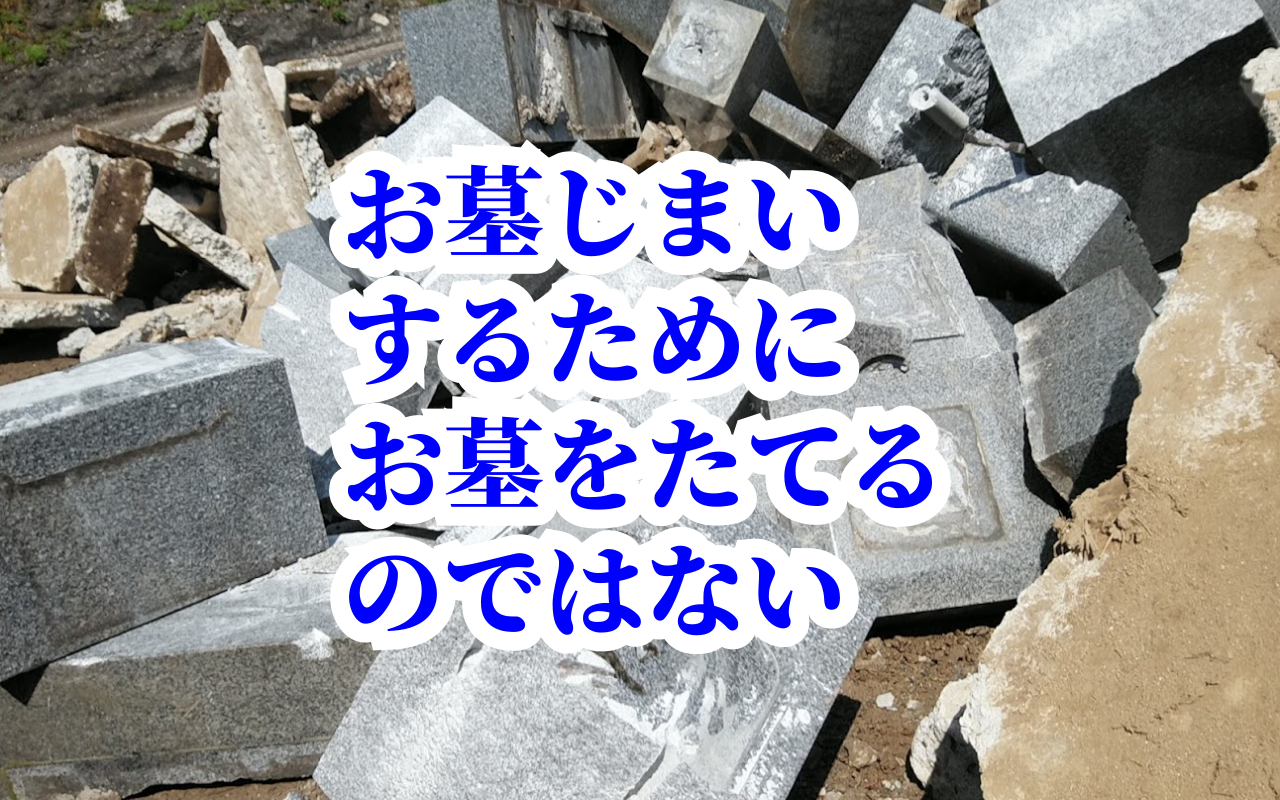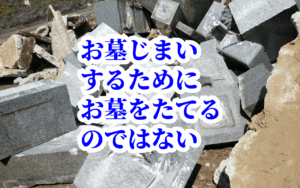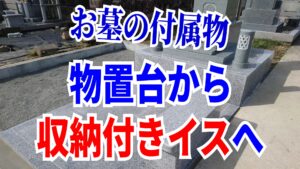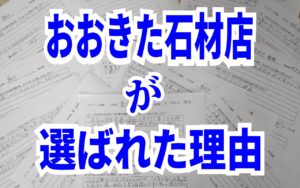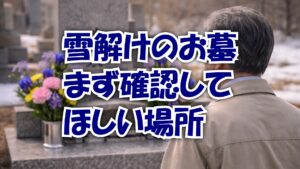「子どもに迷惑をかけたくない」
「将来は墓じまいをするかもしれない」
そんな理由から、お墓を建てること自体をためらう方が増えている、と聞きます。
けれど、そもそもお墓は「しまうため」前提で建てるものではない、「残すため」に建てるもの。
お墓は、“家族の記憶”と“想いの居場所”を未来につなぐために建てるものだと思います。
1. 墓じまいは目的ではなく、結果
お墓じまいとは、お墓が不要になったときに行う「整理」や「終い」の手続きです。
しかし最近は、「いつか墓じまいするから」と、最初から“終わり”を前提に考える方が増えています。
でも実際は――
お墓じまいは、建てた人の思いが途絶えたとき、守る人がいなくなったときに“仕方なく選ぶ結果”であり、最初から予定しておくものではありません。
お墓を建てる目的は、「誰かを想うため」であって、「後で片付ける」ことを前提に建てるものではありません。
2. お墓を建てる人の想い
お墓を建てる人は、未来の管理負担よりも、
「今、きちんと送りたい」「ありがとうを形にしたい」という想いで建てます。
お墓は“面倒の種”ではなく、
「喪失感を持つ人の心を整理する場所」であり、
「残された家族が本来の心の平安を取り戻す場所」です。
そして、何より「亡くなった家族を思い出し、偲ぶ場所」でもあります。
誰かを大切に想う気持ちがある限り、
そのお墓はまだ“生きている”のです。
3. お墓じまいしなくてもいいケース
最近のご相談の中には、
「子どもが遠方にいるから」「誰もお参りしないかもしれないから」といった理由で墓じまいを決める方が多くなっています。
しかし、よく話を伺うと、
- 親戚の中に継承できる人がいる
- 年に数回でもお参りに来ている人がいる
- 管理費の負担は少なく、無理なく続けられる
というケースも少なくありません。
つまり、「本当は墓じまいしなくてもいいお墓」がたくさんあるのです。
お墓じまいは一度してしまうと、二度と元に戻せません。

だからこそ、「本当に必要か」を立ち止まって考えることが大切です。
4. お墓を残すという選択肢
「墓じまいするか、しないか」という二択ではなく、
「どうすれば残せるか」を考えてほしいのです。
たとえば、
- 墓地管理者あるいは施工石材店に相談して、掃除や供花をお願いする
- 親族や地域の人と協力して守る
- 一部を改修して、コンパクトにするなど無理のない形に整える
- 草が生えるのが大変なら、生えない工夫をする
- お参りすることが大変なら近い墓地へ引っ越しする
など、工夫次第でお墓は十分に残せます。
お墓を守るとは、単に石を残すことではなく、
「想いを未来につなぐ工夫をすること」なのです。
5. まとめ
お墓を建てるのは、「墓じまいするため」ではありません。
今を想い、未来を見据えて建てるものです。
お墓じまいが増える時代だからこそ、
「本当に終わらせるべきお墓」と
「まだ終わらせる必要のないお墓」を
しっかり見極めることが大切です。
お墓は、誰かの心を支え続けている限り、
まだその役目を終えていません。
お墓じまいするために建てたお墓など、ひとつもありません。
それぞれのお墓には、誰かを想う気持ちの“はじまり”があるのです。